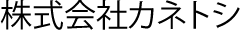ゆず酢を摂って、もっともっと健康になろう

photo/Kazuyoshi Furuichi
※無断転載を禁じます昨年(2002年8月1日 毎日新聞)の日本人の平均寿命は女性が84.93歳、男性が78.07歳となり、男女共2年連続の伸びをしめし、世界1の長寿国になりました。長生きはよいことですが、ぼけて長生きはしたくないものです。しかし体は確実に老化していきます。老化をすこしでも防ぐことはできないのでしょうか?いま医療の分野では格段の進歩があり、薬の開発・遺伝子治療などさまざまな治療がすすめられています。しかし、いくら医学が進歩してもやはり健康で病気をせずに歳をとりたいと誰もが願うことです。そんな願いをかなえてくれるものがあったとしたら・・・・・そこでお酢の登場です。
お酢は古来より万病に効くものとして(かなりひどい症状は別だが・事実が確認できないものもある)利用されてきました。お酢を信仰している永田正松氏によれば酢は命と同じほど大切であるといっています。酢は体の体液を弱アルカリに保ち、病気しらずでボケも防ぐとあります。わたしもこの意見に大賛成です。クエン酸とビタミンCを多く含むゆずは香り・風味この上なく良く毎日食べても決してあきのこないものです。焼き魚や酢の物、ポン酢などと料理としても十分にその魅力を発揮します。それゆえ、ゆず酢を毎日食べて健康で長生きし、美しく老いましょう。
体のなかのエネルギーをとりだす仕組み
私たちは働いたり、運動したり、体温を一定に保ったりと生活に必要なエネルギーを食物をとうしてとり入れています。糖質(ご飯やパン)・タンパク質(肉や魚)・脂質を酸化(燃やして)してATPをつくりこれが活動のエネルギー源となります。
また各栄養素の体の中での運命経路はがあって、糖質・タンパク質・脂質いずれもがクエン酸回路を通ってATPを取り出し、最後は炭酸ガスと水となり排出されます。
疲労回復効果

photo/Kazuyoshi Furuichi
※無断転載を禁じますゆずの成分の中にはクエン酸が多く含まれています。普段酸っぱいものがそれほど好きでない人でも仕事や運動などで疲れた時、梅干しやレモンなど酸っぱい食品を食べたくなった経験は誰でもあると思います。私たちの体は疲れた時に酸っぱい食品を摂ることで疲労の回復が早まることを経験的に知っています。疲れた時は乳酸という物質が血液中に溜まり血液を酸性に傾け、筋肉を硬くさせてしまいます。クエン酸回路の回転がスムーズにいっているときには乳酸はほとんど蓄積されずにATPを供給します。クエン酸回路はクエン酸が重要な役割を果たしていることからつけられた名前です。また生化学者H.Aクレブス博士の名を取ってクレブス・サイクルとよばれています。さて疲労物質である乳酸の蓄積が多くなり分解が間にあわないと、ますます乳酸がたまり急性疲労が増えます。そこでクエン酸を直接取り込むことでATPをつくる速度を速め、また同時に乳酸の分解を高める働きをうながします。その結果疲労が回復するということになるのです。
そこでクエン酸をいっぱい含んでいるゆず果汁をおおいに摂り、疲労知らずの体と健康を心がけたいものです。
抗酸化作用(ビタミンC ・ポリフェノール)

photo/Kazuyoshi Furuichi
※無断転載を禁じます私たちは酸素を取り入れて生きています。酸素というのはほかの多くの元素と結合しやすい性質(酸化性という)をもっているので酸素を含む化合物が周りには多くあります。酸素の強力な反応は酸素分子が特別な電子配置をもっていることによります。2個の酸素原子が酸素分子をつくるときに軌道に逆向きのスピンをもつ電子が2個づつ入ると安定します。軌道に1つの電子しかはいっていないときは不安定でペアをつくろうとします。このペアをつくっていない電子をもつものをラジカルと呼ばれ、活性酸素です。
我々の取り入れた酸素の1~2%は活性酸素になります。このラジカルが体の中の脂質でできている細胞膜を酸化させ、DNAを攻撃し細胞の活動を低下させます。さまざまな病気の原因になることが言われています。たとえば、癌・動脈硬化・糖尿病・炎症・心臓疾患・潰瘍・白内障・ストレスなどです。ただしウイルスを殺すなどプラス働くこともあります。その場合、ビタミンCはラジカルの発生をうながし多すぎると逆にとめる働きをします。
ビタミンCはゆずの中に多く含まれています。特に果皮中には150mgもふくまれておりレモンよりも多い値は驚きです。ビタミンCは体の中では、反応性にとみ、(この場合の反応性は体にとって良い働きをする)悪玉のラジカルを捕らえスキャベンジャーとして作用します。酸化を防止するはたらきのことを抗酸化作用といいます。体の細胞膜は脂質でできているため脂質の酸化を防ぐのにもうひとつのビタミンEが必要です。このビタミンEは酸化型⇔還元型というふうにビタンミンCがあると繰り返し使われ、脂質の酸化を防止します。したがって細胞膜の酸化を補助的に防ぐ働きをすることで体の健康を維持するように働きかけます。

photo/Kazuyoshi Furuichi
※無断転載を禁じますまた、ゆず果皮中や種子のなかにはヘスペリジンやリモノイドなどのポリフェノールが含まれています。ポリフェノールはビタミンCと同様に体のなかでさまざまな働きをする生理活性物質として注目されています。
最近は先ほどの抗酸化作用(フリーラジカル除去作用)、抗変異原性作用と癌や心臓病のような疾病予防への関心が増えつつあるようです。血液のなかには100ml中に標準130~230mgの総コレステロールが含まれており、コレステロールが多くなると動脈硬化になりやすく、心臓・血管系の生活習慣病につながります。
最新のアメリカの実験では柑橘類に含まれる果汁が特に心臓疾患や癌などの慢性疾患の危険を低くするという報告があり、疾病予防および治療において重要な応用性をもつ可能性を秘めています。
また抗酸化ポリフェノール、主にフラボノイドは金属に結合し脂質および他の分子の酸化を抑制するなど抗血栓作用(つまり血液がさらさらとなる)および血管保護効果をもちます。また悪性腫瘍(癌)の進行をいくつかの段階で阻害し、DNA保護・発癌物質の不活化や遺伝子の突然変異発現の阻害、また生体異物の解毒にはたらく酵素を活性化するなど多くの報告があります。
これら食品ポリフェノールの栄養学的意義や健康への有益な効果については詳細な研究が進展しているところです。とりわけゆずに含まれるポリフェノールに大いに期待されます。
健康の体・・弱アルカリ性体質にする
私たちの体の中には、年齢や性別によって違いがありますが、体重の約60%にあたる水分が含まれています。たとえば体重60kg人ならば、36kgが水になります。体液が酸性かアルカリ性かは、体液中の水素イオン濃度(H+)によって決まります。体液中に存在する水素イオン濃度は0.00000002~0.00000016モル(濃度)くらいの小さい数値です。この数値を簡易に表すのがpHで体内では7.35~7.45ぐらいの範囲で弱アルカリ性に保たれています。さて、私たちの必要なエネルギー(ATPエネルギー)をつくりだす間に副生成物として生産された乳酸は酸性物質で細胞から体液へと移行し最終的には腎臓から尿となって排泄されます。この時乳酸の酸性を中和するために体内では重炭酸イオン(アルカリ性)が消費されますが、乳酸が過剰にできた場合や重炭酸イオンが少ししかないなどの条件があるときに、体液が酸性側に傾きます。(アシドーシス)酸性体質になった体内ではさまざまな代謝(体の中の反応)機能が阻害されるために、疲労や病気や体調の変調の要因となっています。酸を摂取することで(クエン酸など)クレブス回路が活発化し乳酸の分解をはやめることがわかっています。例→でんぷんだけを摂取した人の乳酸値とでんぷんと同時にクエン酸を摂取した人の乳酸値とを比べると、10.25→3.77(mg/100ml)に減少していました。(詳細は省略)つまりクエン酸の摂取は体液の酸性側に傾くのを抑制し健康なからだである弱アルカリ体質にするのにとっても役立つことがわかります。古くから梅干をたべたりするのはこのためです。ゆずを是非毎日の健康にお役立て下さい。
かぜにかからない(免疫能力を増強)

photo/Kazuyoshi Furuichi
※無断転載を禁じますかぜというのはそのほとんどがウイルスによる感染が原因で、主に鼻・喉(鼻水・くしゃみ、咳など)上気道の急性炎症を症状とする一群の病気の総称です。インフルエンザはインフルエンザウイルスの感染によるもので多くの種類があります。(代表的なものA・B・C型又新たなものまで)予防接種はあるものの、風邪・インフルエンザに効く治療法はなくほとんどが症状を緩和する対症療法です。
古くより12月22日前後の冬至の日にはゆず湯に入る風習があります。古人の知恵としてゆずが風邪に効くということがわかっていたのでしょう。ゆずの果皮にはビタミンCが多く含まれています。(前章にデータ有り)風邪とビタミンCに関する研究は60年代後半から研究され、70年代に「大量のビタミンCがかぜに効く」ということをポーリング氏が発表しています。これをきっかけに新しい観点からビタミンCの研究が現在も行われています。さまざまな実験結果からまとめると、日頃より摂取した場合は風邪にたいする抵抗力を高める傾向にあり、風邪の引き始めに(おかしいと感じ始めたときに)ビタミンCの回数を重ねて摂るのが最も効果的であるようです。わが国でも認識されはじめています。かつての欠乏症に対する治療から現在では、生活習慣病(癌・心臓病・脳卒中)などの予防効果へと、ますますビタミンCの新しい知識が集積されつつあるようです。ゆず茶やゆずドリンクなどでゆず湯などで身も心も温まりましょう。
現代人の病気ストレスを緩和しよう果

photo/Kazuyoshi Furuichi
※無断転載を禁じます現代人はほとんどストレスを抱えて生活をしていると言っていいくらいさまざまなストレスがあふれています。たとえば、新しいところから過労・能力主義・リストラ・会社の倒産・将来の不安・テクノストレス・騒音・気候(暑い寒い)・感染・株の暴落・健康・人間関係・老後・などです。ここでもビタミンCは有効です。私たちはストレスを受けると脳の中の下垂体というとところから指令が下り副腎でホルモンやアドレナリンなどの分泌によってストレスをはねかえそうとします。このホルモンの生成にビタミンCの生成量が増大します。ストレスを受けると、体のビタミンCが減少します。人はビタミンCをつくれないのでストレスを受けた時はビタミンCを多く摂るようにしましょう。
美肌をつくろう
いつまでも若く、美しくありたいのは女性の望みです。また年をとっても美しく老いたいものです。美しい肌は皮膚の最外層にある角質層の水分が十分にあり、保湿因子(アミノ酸、尿素、電解質など)、皮膚表面の脂肪分のバランスがとれている状態です。表皮は大まかに分けて、角質層・顆粒層・基底層があります。角質層はたえず新しい細胞といれかわり、古い細胞は垢となってはがれていきます。常に新しい細胞と入れ替わって再生しています。基底層には色素細胞(メラノサイト)が存在しており、メラニンは紫外線から皮膚を守る働きをしています。メラニンは濃い色のものと無色のものがあり、シミは濃い色のもの顔面に沈着したものです。メラニンはチロシンというアミノ酸からできます。このときにビタミンCがチロシンからのメラニンの生成を抑えます。またコラーゲンは細胞の増殖を促し美しい素肌をつくるためにひつようです。さらにペクチン質が皮膚の保護効果を高めることもいわれています。これら美肌にとって有効な成分がゆずには豊富にふくまれています。
参考文献
- 食品の科学 果実の科学 伊藤三郎編 朝倉書店
- 5訂最新食品成分表 科学技術庁資源調査会編5訂日本食品標準成分表準拠
- 食品学総論 森田潤司/成田宏史 科学同人
- 新ビタミンCと健康 村田晃 共立出版
- 月間フードケミカル2 各書
- 改訂ウェルネス栄養学 西原照代 西原 力 建ぱく社
- 薬を減らして酢(クエン酸)を飲もう 永田正松 健友館
- ゆず栽培から加工・利用まで 音井 恪
- Polyphenols:Chemistry,Dietary Sources, Metabolism and Nutritional Significance
著書 Laura Bravo - Polyphenol antioxidants in citrus juices : in vitro and in vivo studies relevant to heart disease.
(Vinson JA, Liang X, Proch J, Hontz BA, Dancel J,Sandone N.) - 果実その他資料提供 有限会社カネトシ
- 著者プロフィール 久村 文恵 (ひさむら ふみえ)
管理栄養士 兵庫医科大学小児科学教室勤務(実験・検査)
大阪市立大学大学院修士課程 食品学専攻(生体防御反応に関する研究)
自称ゆず愛飲家。